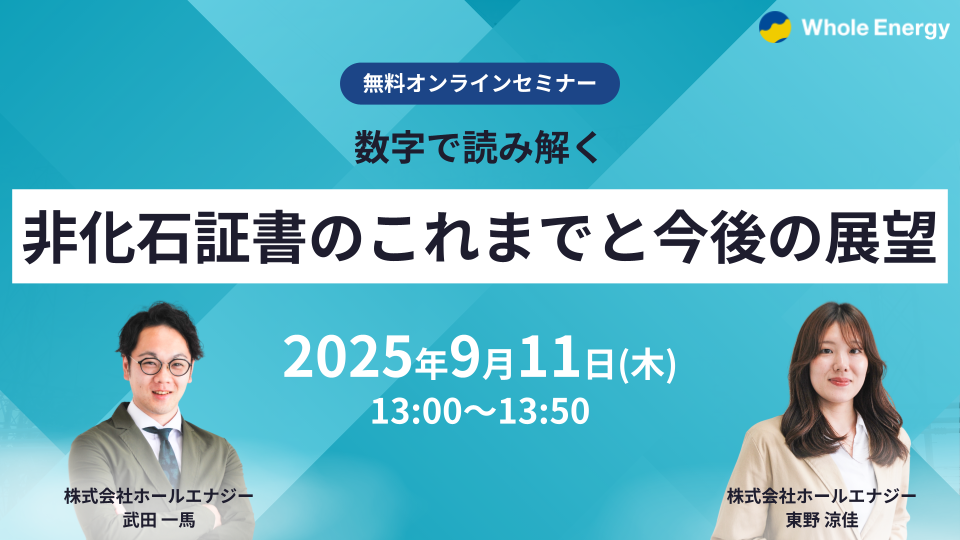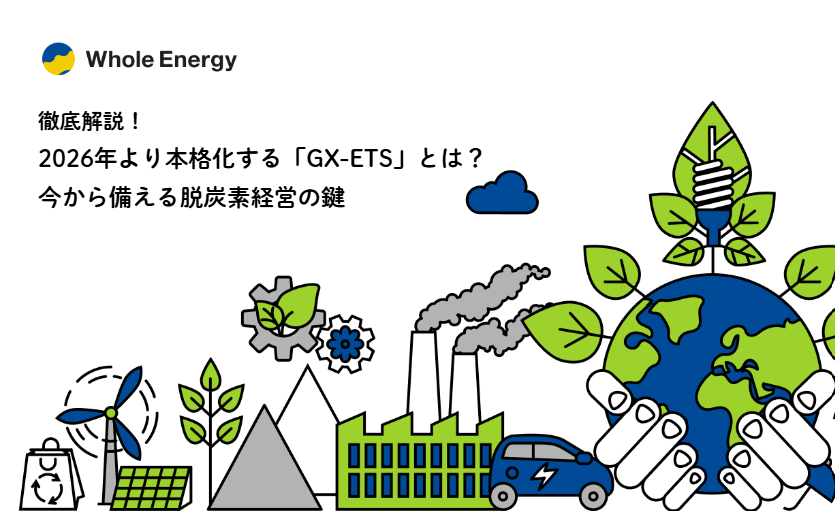夏の電気代請求でコスト高を実感した企業様へ、対策のご提案

電気代高騰が突きつける経営リスク
2025年夏、前年より20%増の請求書が届いた!
冷房や生産設備の稼働増加により電力使用量が増える時期ではありますが、ここ数年の上昇幅は従来の想定を超えています。
特に製造業や物流業、小売業など電力多消費型の産業では前年同月比で二割を超える増加が報告されました。
原材料価格や人件費の上昇と重なることで価格転嫁が難しく、中堅・中小企業にとっては深刻なリスクとなっています。
電気代はもはや「管理コスト」ではなく「経営課題」として正面から向き合う必要があるのです。
電気料金が高止まりする構造的要因
電気料金の上昇は一時的な現象ではなく、複数の構造的要因が同時に作用しています。
まず燃料費調整額です。
国際的にLNGや石炭の価格は2022年をピークに下落していますが、日本の電力会社は長期契約中心の調達構造を持つため、スポット価格の低下が即座に反映されるわけではありません。
さらに円安が続き、ドル建てで下落しても円換算では高止まりしており、燃料費調整額を押し上げています。
※直近では政府の補助金によって値下がり傾向にありましたが、2025年10月分からは補助金が縮小されるため、再び上昇する見通しです。
次に制度的コストです。
2025年度の再エネ賦課金は1kWhあたり3.98円と過去最高を更新しました。
前年度比で14%上昇しており、年間100万kWhを使用する企業の場合、総負担額は約398万円となり、前年度2024年(3.49円/kWh)と比べて約49万円の追加負担が発生します。
加えて猛暑による空調需要やデータセンター稼働増など、需要構造の変化も市場価格の変動を拡大し、電気料金を押し上げる要因になっています。
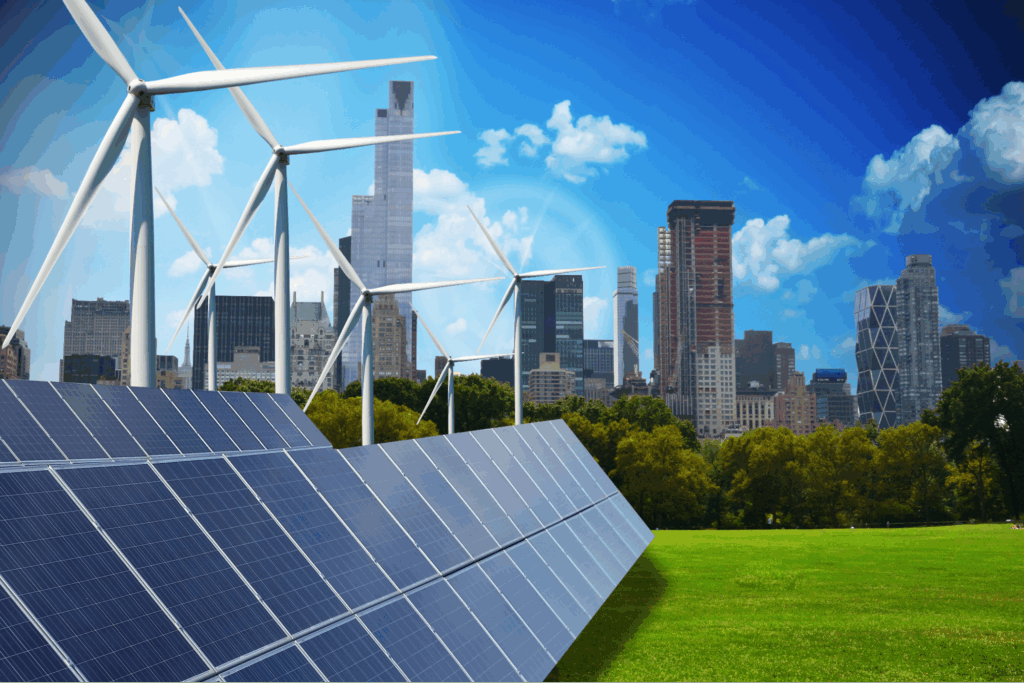
企業が取るべき具体的対応策
こうした状況で有効なのは、単なる節電ではなく、調達戦略と利用最適化の両輪です。
小売電気事業者との契約再交渉や入札(オークション)方式による見直しは、特に高圧・特別高圧を利用する企業に大きな効果をもたらします。
実際に年間で10〜15%のコスト削減に成功した事例も報告されています。
参考:長期契約の解約清算金を大きく上回るコスト削減を実現した、外資系食品メーカー工場
さらに、エネルギーマネジメントシステムを活用して電力使用量を部門別・時間帯別に可視化すれば、データに基づいた効率的な改善が可能になり、こうした取り組みは無駄をなくすだけでなく、将来的な投資判断の基盤ともなります。
再生可能エネルギーの導入も調達リスク軽減に直結します。
オンサイト型太陽光や蓄電池を組み合わせたモデルは、調達コストを固定化しつつ非常時のレジリエンスも高め、再エネ発電事業者と直接契約を結ぶコーポレートPPA(長期電力購入契約)では、価格変動リスクを回避しながら脱炭素経営の推進にもつながり、欧州では一般化しております。
日本でも大手企業を中心に導入が進んでいます。
脱炭素とコスト最適化の一体化へ
電力コスト最適化は経費削減にとどまらず、脱炭素経営と不可分のテーマです。
サプライチェーン全体で排出削減が求められるなか、再エネ導入や省エネ投資は投資家や金融機関からの評価向上につながり、新規取引や資金調達条件の改善といった副次的効果を生みます。
逆に対応を怠れば、炭素コストの上昇や国際競争力の低下に直結するリスクが高まります。
2025年夏の請求額は、企業にとって「従来の延長線では対応できない」という明確なシグナルです。
燃料価格や制度的負担、需要動向といった要因が複雑に絡む以上、改善を待つだけでは不十分で、契約内容の精査、利用状況の見える化、再エネ調達戦略の策定など、すぐにでも着手すべき課題は多く存在します。
当社では契約診断やEMS(エネルギーマネジメントシステム)導入、コーポレートPPA設計など幅広く支援しています。まずは現状の把握から始めてみませんか?
費用はかからず、無料診断からスタートできます。
出典:https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/


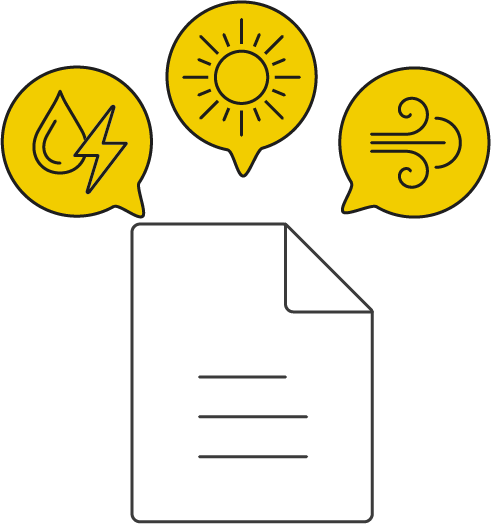 非化石証書購入代行サービス
非化石証書購入代行サービス
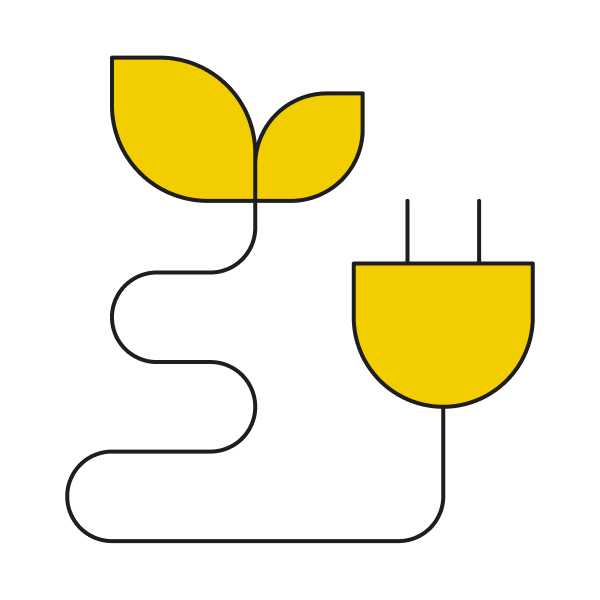 再エネ導入コンサルティング
再エネ導入コンサルティング
 電気料金比較サービス
電気料金比較サービス